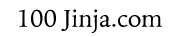竈門神社(かまどじんじゃ)は、福岡県太宰府市にある神社。式内社(名神大社)。旧社格は官幣小社で、現在は神社本庁の別表神社。別称を「宝満宮」「竈門宮」とも呼ばれる。
太宰府市東北に立つ宝満山に所在する神社で、社殿は次の2ヶ所に形成されている。
上宮 – 宝満山山頂(標高829.6メートル)。
下宮 – 宝満山山麓。
宝満山は大宰府の鬼門(東北)の位置にあることから、当社は「大宰府鎮護の神」として崇敬された。平安時代以降は神仏習合が進み、当社と一体化した神宮寺の大山寺(だいせんじ、竈門山寺・有智山寺とも)は、西国の天台宗寺院では代表的な存在であった。今なお福岡県下には当社から勧請された約40社の神社があり、現在も宝満山に対する信仰・縁むすび信仰により崇拝されている神社である。
主祭神
玉依姫命 (たまよりひめのみこと)
相殿神
神功皇后 (じんぐうこうごう)
応神天皇 (おうじんてんのう) – 第15代。神功皇后皇子。
社伝では、天智天皇の代(668年-672年)に大宰府が現在地に遷された際、鬼門(東北)に位置する宝満山に大宰府鎮護のため八百万の神々を祀ったのが神祭の始まりという。次いで天武天皇2年(673年)、心蓮(しんれん)上人が山中での修行していると玉依姫命が現れたため、心蓮が朝廷に奏聞し山頂に上宮が建てられたという[6][5]。神社側では、この時をもって当社の創建としている。
これらの社伝の真偽は明らかではないが、下宮礎石群の調査から創建は8世紀後半には遡るとされる。また上宮付近からは、9世紀から中世にまで至る、多くの土師器・皇朝銭等の祭祀遺物が検出されており、大宰府・遣唐使との関連も指摘される。