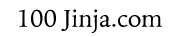佐太神社(さだじんじゃ)は、島根県松江市鹿島町佐陀宮内にある神社。出雲国二宮である。出雲國神仏霊場第四番。
秋鹿郡佐田大社之記に垂仁54年の創建で、養老元年(717年)に再建されたとある。『出雲国風土記』の記述からもとは神名火山(現:朝日山)のふもとに鎮座していたと考えられる。
『出雲国風土記』秋鹿郡条に「佐太御子社」と記載されている。延喜式神名帳には「佐陀神社」と記載されている[1]。中世に入ると「佐陀大明神」とか「佐陀大社」、「佐陀三社大明神」などと呼ばれるようになった。明治に入り現在の「佐太神社」に改称した。
康元元年(1256年)の『社領注進状』(出雲大社所蔵)によれば280丁と、杵築大社(現:出雲大社)に匹敵するほどの社領を有していたという。
江戸時代に入ると杵築大社とともに出雲国内の神社を管轄しそれらを支配する「触下制度」を確立した。佐陀大社の管轄は島根郡、秋鹿郡、意宇郡の西半分と楯縫郡の神社であった。