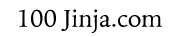高瀬神社(たかせじんじゃ)は、富山県南砺市高瀬にある神社。式内社、越中国一宮。旧社格は国幣小社で、現在は神社本庁の別表神社。
富山県西南部、南砺市の東方に鎮座する。
律令制下に神階では越中国で最高位を占め、一宮であったとされる。なお越中国一宮を名乗る神社としては、当社のほかに射水神社、気多神社、雄山神社がある。
戦国時代には戦乱で荒廃したが、江戸時代に加賀藩主・前田氏の崇敬を受けて手厚く保護された。
主祭神
大己貴命(大国主命)
配神
天活玉命
五十猛命
このほか礪波郡内の氏神と越中国内の式内社34座の神を祀る。
創建の年代は不明。大己貴命が北陸平定を終えて出雲へ戻る時に、国魂神として自身の御魂をこの地に鎮め置いたのに始まると伝えられるが、景行天皇の治世であるとも伝えられる。
当社は「高瀬神」の名で度々六国史に登場し、神階の陞叙を受けている。以下は時系列で並べた神階の授与である。
いずれの陞叙も射水神社と同時・同階で、共に越中国最高位の神社として朝野の崇敬を受けていた。 『日本文徳天皇実録』斉衡元年(854年)12月27日の条では、高瀬神の祢宜と祝(はうり)が把笏に預かったことが記載されているが、古代に笏を把ることを許されたのは伊勢神宮と諸大社の神職のみであったと言う。
延長5年(927年)には『延喜式神名帳』により小社へ列せられ、礪波郡の式内社7座の筆頭に記載された。
平安時代の末に一時国府が礪波郡に移転したことから、それ以降、越中国一宮とされた。神仏習合の神社であり、三百坊の勧学院を擁していた。
中世、越中国の一向宗徒の支配下に入った。その際、一部の神職が雄神神社に転じている。
戦国時代の戦乱により荒廃したが、江戸時代に加賀藩主・前田氏の崇敬を受け、手厚く保護された。
明治6年(1873年)に県社、大正12年(1923年)に国幣小社に列せられた。戦後は別表神社となった。