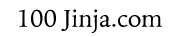鳥海山大物忌神社(ちょうかいさんおおものいみじんじゃ)は、山形県飽海郡遊佐町にある神社。式内社(名神大社)、出羽国一宮。旧社格は国幣中社で、現在は神社本庁の別表神社。
鳥海山頂の本社と、麓の吹浦(ふくら)と蕨岡の2か所の口之宮(里宮)の総称として大物忌神社と称する。出羽富士、鳥海富士とも呼ばれる鳥海山を神体山とする。当社は鳥海山の山岳信仰の中心を担ってきており、平成20年(2008年)3月28日に神社境内が国の史跡へ指定されている。
大物忌大神
主祭神。記紀には登場しない神で、謎が多い。『神祗志料』や『大日本国一宮記』では、大物忌大神と倉稲魂命が同一視されている。
豊受姫命
月読命 – 吹浦口之宮で祀られている
鳥海山は、古代には国家の守護神として、また古代末期からは出羽国における山岳信仰の中心として現在の山形県庄内地方や秋田県由利郡および横手盆地の諸地域など周辺一帯の崇敬を集め、特に近世以降は農耕神として信仰されてきた。
景行天皇または欽明天皇時代の創建と伝えられるが、諸説があり、山頂社殿が噴火焼失と再建を繰り返しているための勧請も絡んでいて、創建時期の特定は困難である。鳥海山の登山口は、主要なものだけで矢島、小滝、吹浦、蕨岡の4ヶ所(鳥海修験 も参照のこと)があり、各登山口ごとに異なる伝承が伝わるうえに、登山口ごとに信徒が一定の勢力を構成して、互いに反目競争することも多かったため、それらの伝承が歪められることも多く、定説をみない状況である.
越国より始められた夷征は、慶雲から和銅の頃に庄内以北の着手に至ったが、当時この地方は原生林に覆われ、また南方を追われた蝦夷が群居し、常に噴煙を吐き時々大爆発する鳥海山の存在は朝廷軍にとって脅威であった。そのような状況で、もともと日本では山岳信仰が盛んだった背景もあって、朝廷は鳥海山の爆発が夷乱と相関していると疑ったのではないか、と『名勝鳥海山』では推測している。